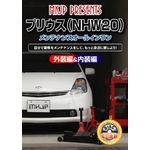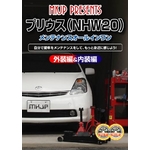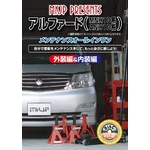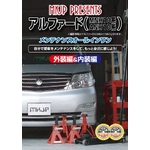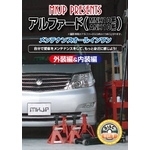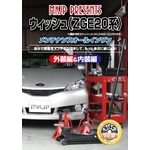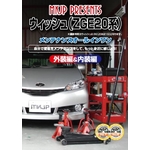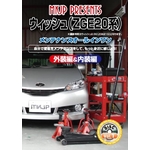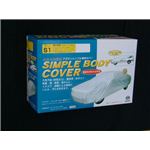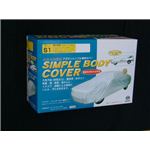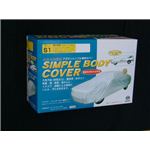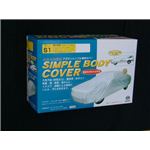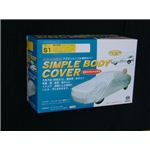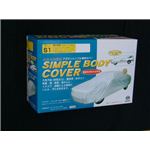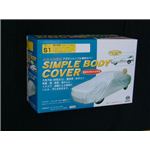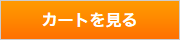新着商品
-
プリウス(NHW20)メンテナンスDVD Vol.1(方法や改造の仕方など)
2,799円
-
プリウス(NHW20) メンテナンスDVD 1-2セット
3,799円
-
アルファード(MNH10系/ANH10系) メンテナンスDVD Vol.2
2,799円
-
アルファード(MNH10系 ANH10系)初心者向け メンテナンスDVD Vol.1 Vol.2セット(方法や改造の仕方など)
3,799円
-
アルファード(MNH10系/ANH10系) メンテナンスDVD Vol.1
2,799円
-
ウィッシュ(ZGE20系/ZGE21系/ZGE22系/ZGE25系) メンテナンスDVD Vol.2
2,799円
-
ウィッシュ(ZGE20系/ZGE21系/ZGE22系/ZGE25系) メンテナンスDVD Vol.1 Vol.2 セット
3,799円
-
ウィッシュ(ZGE20系/ZGE21系/ZGE22系/ZGE25系) メンテナンスDVD Vol.1
2,799円
-
【アラデン】MV6 ARADEN 背高RV ボディーカバー
11,550円
-
【アラデン】MV5 ARADEN 背高RV ボディーカバー
12,600円
-
【アラデン】MV4 ARADEN 背高RV ボディーカバー
12,600円
-
【アラデン】MV3 ARADEN 背高RV ボディーカバー
13,650円
-
【アラデン】MV2 ARADEN 背高RV ボディーカバー
13,650円
-
【アラデン】MV1 ARADEN 背高RV ボディーカバー
14,700円
-
【アラデン】S2W ARADEN シンプルボディーカバー
8,967円
-
【アラデン】S - L ARADEN シンプルボディーカバー
8,967円
-
【アラデン】S5 ARADEN シンプルボディーカバー
8,190円
-
【アラデン】S4 ARADEN シンプルボディーカバー
8,190円
-
【アラデン】S3 ARADEN シンプルボディーカバー
8,190円
-
【アラデン】S2 ARADEN シンプルボディーカバー
8,190円
-
【アラデン】S1 ARADEN シンプルボディーカバー
8,190円
-
【アラデン】CCB-S ARADEN 防炎自転車カバー 小径車・折りたたみ自転車カバー
3,307円
-
【アラデン】CCB-H ARADEN 防炎自転車カバー ハイバックシート付
4,095円
-
【アラデン】CCB-M ARADEN 防炎自転車カバー MTB
3,307円
-
【アラデン】CCB-T ARADEN 防炎自転車カバー 2台用
3,570円
-
【アラデン】CCB-C ARADEN 防炎自転車カバー シティ
3,129円
-
【アラデン】NO.91 ARADEN 小径車・折りたたみ自転車カバー
2,646円
-
【アラデン】NO.71 ARADEN ハイバックシート付自転車カバー
2,803円
-
【アラデン】NO.41 ARADEN 2台用自転車カバー
2,992円
-
WONDAX-H(ワンダックス・ハード) 120ml 【WONDAX-1処理車専用ボディ保護剤】
5,145円
自動車(じどうしゃ)とは、原動機の動力によって陸上を走行する車両のうち、軌条によらずに運転者の操作で進路と速度を変えることができる乗り物である[要出典]。英語ではautomobile、motorcarなどという。
目次 [非表示]
1 概要
2 歴史
2.1 共有の歴史
2.2 個人所有の歴史
3 産業
4 社会に及ぼす影響
4.1 交通問題
4.2 環境問題
4.3 その他の問題
4.4 人体への影響
5 スポーツ、趣味としての自動車
6 分類
7 構造
7.1 車体構造
7.2 原動機
7.3 動力伝達
7.4 操舵装置
7.5 制動・拘束装置
7.6 運転装置
8 サービス業
9 脚注・出典
10 関連項目
11 外部リンク
概要[編集]
一般的には、三輪以上で乗員が車室内に備えられた座席に座る構造を備えたものを「自動車」として認識されているが[要出典]、法規上はオートバイや無限軌道によって走行する車両、他の自動車によって牽引される車両も自動車として定義されている。一方、排気量が50cc以下(または定格出力が0.6kW以下)の車両(ミニカーを含む)や架線を用いるトロリーバスは法規上の「自動車」に含まれない。
英語のautomobileはフランス語を語源としていて、カタカナでは基本的に「オートモービル」と表記される。日本語の自動車という単語は、先述のautomobileに由来しており、"auto"は「自ら」、"mobile"は「動くもの」という意味を持つことから作られた。同じ漢字圏でも中国語では別の語を、韓国語では日本語由来の語を用いる。英語で単にcarと言った場合、馬車や鉄道車両なども含めた車両全般を指す。
自動車を動かすこと、操ることを運転という。ロボットカーとも呼ばれる自動運転技術も研究されている。主に人や荷物の輸送手段として用いられるが、運転操作自体を娯楽やスポーツとしたり、所有すること自体を趣味として保有されるほか、単なる資産として保有されたりといった例も少なくない。特に高級車の保有はステータスシンボルとしての意味合いがある。
歴史[編集]
Question book-4.svg
この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。(2011年4月)
マルクスカー
最初の自動車は蒸気機関で動く蒸気自動車で、1769年にフランス陸軍の技術大尉ニコラ=ジョゼフ・キュニョーが製作したキュニョーの砲車であると言われている。この自動車は前輪荷重が重すぎて旋回が困難だったため、時速約3キロしか出なかったにもかかわらず、パリ市内を試運転中に塀に衝突して自動車事故の第一号となった[1]。イギリスでは1827年ごろから定期バスとして都市部および、都市間で広く用いられ、1860年ごろにはフランスでも用いられるようになった[要出典]。1885年に、フランスのレオン・セルボレが開発し1887年に自動車に搭載したフラッシュ・ボイラーにより蒸気自動車は2分でスタートできるまでに短縮された。1900年ごろにはアメリカ合衆国で、石炭の代わりに石油を使った蒸気自動車が作られ、さらに普及していった。この頃は蒸気自動車の方がガソリン自動車よりも騒音が少なく運転が容易だった。アメリカ合衆国では1920年代後半まで蒸気自動車が販売されていた。
1865年にイギリスで赤旗法が施行された。当時普及しはじめた蒸気自動車は、道路を傷め馬を驚かすと敵対視されており、住民の圧力によってこれを規制する赤旗法が成立した。この法律により、蒸気自動車は郊外では4マイル(6.4km)/h、市内では2マイル(3.2km)/hに速度を制限され、人や動物に予告するために、赤い旗を持った歩行者が先導しなければならなくなった。イギリスでの蒸気自動車の製造、開発は、この赤旗法が廃止される1896年まで停滞することになり、それに続くガソリン自動車の開発においても、ドイツやフランスが先行する事になる。
1885年型ベンツ
1870年、ユダヤ系オーストリア人のジークフリート・マルクス(Siegfried Samuel Marcus)によって初のガソリン自動車「第一マルクスカー」が発明された。1876年、ドイツのニコラウス・オットーがガソリンで動作する内燃機関(ガソリンエンジン)をつくると、ゴットリープ・ダイムラーがこれを改良して二輪車や馬車に取り付け、走行試験を行った。1885年にダイムラーによる特許が出されている。1885年、ドイツのカール・ベンツは、ダイムラーとは別にエンジンを改良して、車体から設計した3輪自動車をつくった。ベンツ夫人はこの自動車を独力で運転し、製造者以外でも訓練さえすれば運転できる乗り物であることを証明した。ベンツは最初の自動車販売店を作り、生産した自動車を数百台販売した。また、ダイムラーも自動車会社を興した。現在、ガソリン式自動車の発明者はダイムラーとベンツの両人とされることが多い。
初期の自動車は手作りであるため非常に高価なものであり、貴族や大金持ちだけが所有できるものであった。そして彼らは自分たちが持っている自動車で競走をすることを考えた。このころに行われた初期の自動車レースで活躍したのが、今日もF1などで活躍するルノーである。このころはまだガソリン自動車だけでなく蒸気自動車や電気自動車も相当数走っており、どの自動車が主流ということもなかったが、1897年のフランスでの自動車レースでガソリン自動車が蒸気自動車に勝利し、1901年にはアメリカのテキサスで油田が発見されてガソリンの供給が安定する一方、電気自動車や蒸気自動車は構造上の問題でガソリン自動車を越えることができず、20世紀初頭には急速に衰退していった[2]。
フォード・T型
1908年には、フォードがフォード・T型を発売した。フォードは、流れ作業による大量生産方式を採用し自動車の価格を引き下げることに成功した。これにより裕福層の所有物であった自動車を、大衆が所有することが可能となり自動車産業が大きく発展するさきがけとなった。ヨーロッパでは1910年ごろに、大衆の自動車に対する欲求を満たすように、二輪車の部品や技術を用いて製造された小型軽量車、いわゆるサイクルカーが普及していった。1922年に、フォードと同様の生産方法を用いたシトロエン・5CVやオースチン・セブンなどの小型大衆車が発売され、本格的に自動車が普及していく事になった。また、それに伴いサイクルカーは姿を消していくことになる。
電気自動車や燃料電池を動力源とした自動車もあり、前者は今でもトロリーバスとして存在している車両もある。
上記のT型フォードなどの大衆車の普及によって、一般市民が自動車を所有することが可能となり、自家用車が普及すると、それに伴って自動車を中心とする社会が形成されるようになり、自動車が生活必需品となっていく、いわゆるモータリゼーションが起こった。世界ではじめてモータリゼーションが起こったのは1920年代のアメリカ合衆国であり、次いで西ヨーロッパ諸国においても起こり、日本でも1970年ごろに本格的なモータリゼーションがはじまった。個人用自動車の普及は、鉄道や船といった公共交通機関に頼っていた時代に比べて利用者に圧倒的に高い自由度をもたらし、個人の行動半径を大きく拡大させることとなった[3]。
- 更新情報
-
- 2014.03.30 "プリウス(NHW20)メンテナンスDVD Vol.1(方法や改造の仕方など) " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "プリウス(NHW20) メンテナンスDVD 1-2セット " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "アルファード(MNH10系/ANH10系) メンテナンスDVD Vol.2 " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "アルファード(MNH10系 ANH10系)初心者向け メンテナンスDVD Vol.1 Vol.2セット(方法や改造の仕方など) " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "アルファード(MNH10系/ANH10系) メンテナンスDVD Vol.1 " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "ウィッシュ(ZGE20系/ZGE21系/ZGE22系/ZGE25系) メンテナンスDVD Vol.2 " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "ウィッシュ(ZGE20系/ZGE21系/ZGE22系/ZGE25系) メンテナンスDVD Vol.1 Vol.2 セット " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "ウィッシュ(ZGE20系/ZGE21系/ZGE22系/ZGE25系) メンテナンスDVD Vol.1 " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "【アラデン】MV6 ARADEN 背高RV ボディーカバー " を販売開始しました。
- 2014.03.30 "【アラデン】MV5 ARADEN 背高RV ボディーカバー " を販売開始しました。